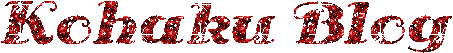
Produced & Photographed by Matsutora
わが庭の生き物たち
平成30年6月30日 〜 7月29日
CREATURES IN MY GARDEN
June 30 - July 29 , 2018
ハクセキレイとカンナ
ハクセキレイは毎日のように顔を見せてくれる。(6月30日)

水田に水が入ってから約3週間、シラサギが今年も水田に帰ってきた。
これから約3か月間、餌を食べに毎日に飛来することだろう。(7月2日)

ムクドリが生垣の笹の下で休息していた。(7月5日)

毎年ハグロトンボが生垣の竹藪やその傍の木陰で生活している。
幼虫は、ヨシ、エビモ、バイカモなどが茂る緩やかな流れに生息し、6〜7月頃に羽化する。
羽化後の若い個体は薄暗いところを好み、水域から離れて林の中などで生活する。
この時期にわが庭にやってくるようだ。
成熟すると再び水域に戻り、明るい水辺の石や植物などに止まり縄張りを張る。
交尾後、雌は水面近くの水中植物に産卵する。
写真はわが庭に生息するハグロトンボ(雄)。(7月8日)

ヒメウラナミジャノメ(7月12日)

ハクセキレイが子供(幼鳥)を連れてやってきた。
幼鳥は巣立ちしたばかりらしくまだ自分で獲物や食物を獲得できないようだ。
親鳥に餌をねだっている。(7月12日)

親鳥はすぐに飛び立ったが、残された幼鳥はずっとここで待っていた。

ちょうど一か月前に植えたヤマアジサイに、
ごみが付ているのかと思たったら、(7月14日)

セミの抜け殻だった。

ニシキギにも桜にもロウバイにもあった。
なんとアマゾンでは、セミの抜け殻が5個で545円+送料で売られている。
いったい何に使うんだろうか?参考

追記1: 閲覧者からメールをいただいて、なるほどと手を打った。
「子どもの自由研究などで使うみたいですよ」ということだった。(7月16日)
追記2: 別の閲覧者からメールをいただいた。
「ずっと前、長野出身の方が、カレーにセミの抜け殻をいれられました。
バレーボール大会の昼休み、野外でカレーを作って食べる時の出来事でした。
ずっと後で、長野出身の方に
「カレーにセミの抜け殻を入れるとおいしいと言われ、放り込まれた」というと、
「長野ではそんなことしない」と怒られました」(7月17日)
追記3: 検索してみると、「珍食材百景」レベルではあるが、あちこちで食されているようだ。
高知ではセミの抜け殻に魚のすり身を入れて揚げたものを食べると、意外とうまいらしい。
山梨県ではみそ汁の具にを入れるらしい。天かすのようなサクサクの食感だそうだ。
沖縄では、セミ本体も抜け殻も食するそうだ。
唐揚げや佃煮、田作りのように飴を絡ませたり、など調理法は豊富で、
祖母や母、代々受け継いできた料理だそうだ。
ドラえもんもシチューにセミを入れている。 参考
また、スジアカクマゼミの抜け殻を乾燥させたものは、
「蝉退(センタイ)」や「蝉蛻(センゼイ)」と呼ばれる生薬として利用されている。
風邪などの発熱や悪寒、じんましんなどの皮膚のかゆみ、
咽喉炎や結膜炎などの炎症に効くといわれている。(7月17日)
追記4: そういえば、セミの抜け殻は「空蝉」である。
源氏物語などの古典文学ではおなじみだ。
源氏物語の中の「空蝉」のことはよく記憶に残っている。
光源氏は人妻(空蝉)に恋するが、その夫は、伊予国の男性だった。
源氏物語の中で居住地が伊予国と描かれていたのは彼だけだったと記憶している。(7月17日)
まだセミの声は聞こえないが、近いうちに真夏を彩るセミの競演が聞こえるだろう。

キマダラカメムシ
台湾から東南アジアを原産地とする外来生物である。
1770年代に長崎県の出島で最初に発見され、
1783年に南方系の外来種であると記載されている。
その後各地に分布を拡げたとみられている。
近年急速に分布を北上させていて、2006年には岡山県で確認された。
その後も急速に分布を拡大し、2010年には東京都、
2011年には愛知県で生息が確認されている。(7月15日)

ウスバキトンボ
あまり飛び回らずいつも樹葉に止まって休んでいる。(7月16日)

アオバハゴロモ(芸者という名の昆虫)
アオバハゴロモ(青羽羽衣)という美しい名前の昆虫がいる。
日本では本州以南、国外では台湾、中国に分布する。
幼虫は、白装束に白粉に塗れたようになっているので、
うどん粉病か何かではないかと勘違いする向きもある。
成虫になると、羽は美しい薄緑色で、かわいらしい顔をしている。
この虫は、これらの地域では大変ありふれていて、誰も気にも留めないが、
学名にも「芸者」という美しい名前がつけられて興味を引く。
アオバハゴロモの学名はGeisha distinctissimaである。
イギリス人の昆虫学者フランシス・ウォーカー (Francis Walker、
1809年7月31日 - 1874年10月5日)が名付けている。
おそらく幕末頃に来日したのかもしれないが、その記録は残っていないし、
なぜゆえに「芸者」なのかの記録も残っていない。
つまり経緯は何も分かっていないのである。
日本の高名な昆虫学者は、おそらく前翅の翡翠色やその末端の紅色、
後翅の乳白色などの美しさからの連想ではないかと書き残している。(7月17日)

ミノムシ
絶滅危惧種になっている。
「オオミノガヤドオリバエ」という中国産の寄生蠅が
ミノムシの中身を食い荒らして絶滅しかかっていると言われている。
ミノムシの形態は微笑ましくて好きではある。(7月18日)

蝉の抜け殻はたくさんある。
蝉もいるはずであるが、やっと目の前に現れてくれた。
アブラゼミだった。鳴き声もたまに聞こえてくるようになった。

午前5時半、変なものを見つけた。(7月25日)

7〜8時間かかって、縦のもが横になった。よく見ると羽根らしきものが見える。

午後16時前には、なんと二つに分かれていた。

午後20時、モンクロシャチホコだった。実は交尾していたのだ。
開始時間が定かではないが、わかっているだけでもなんと9時間も合体していた。

モンクロシャチホコは、幼虫の毛虫が初夏から秋にかけてサクラに発生し、
サクラの葉を食べて成長し、このあと地面にもぐって蛹になって越冬し、
翌年、成虫のガになるらしい。
毛虫は、見た目が悪く毒虫のように見えるが、毒はなくて無害であるだけでなく、
なんと食べられるんだそうだ。愛好家の間では有名で、
茹でてからさっと炒めるとサクラの香りがして旨みも強くて美味しいんだそうだ。

東から西に進むという未曾有の台風が通過する日曜日の朝
当地はまだ雨も降らず、強い風も吹いていない。(7月29日)

蝶がアメリカハナミズキの樹葉上で羽を休めていた。

キタテハ(秋型)のようだ。

松虎還暦塔(MATSUTORA 60 TOWER)
還暦時に設置した記念塔。
この場所は、かつては立派な松を植えていたが、
数年前から松枯れ病で徐々に枯れてきていたが、この春はついに枯完した。
一か月前、塔の周辺にヤマアジサイ、ニシキギ、酔芙蓉を植えた。

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作
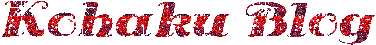
© 2018-2028 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.